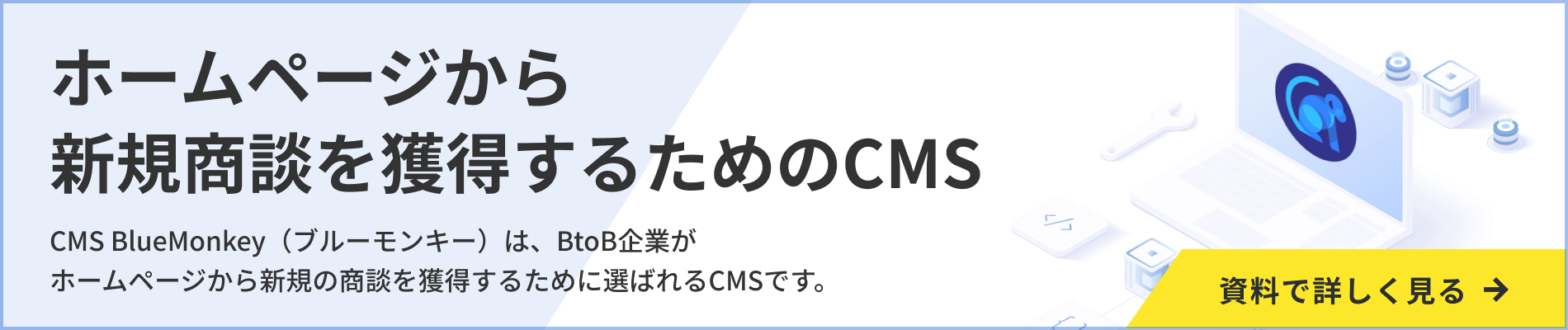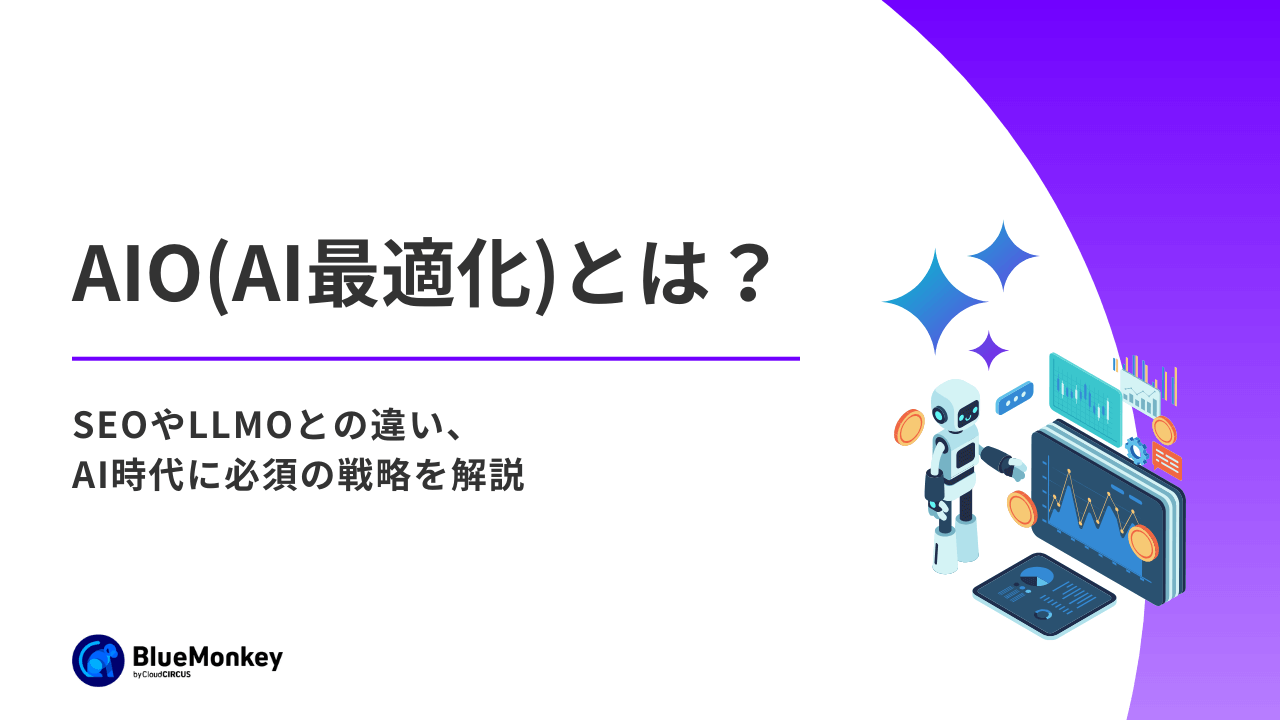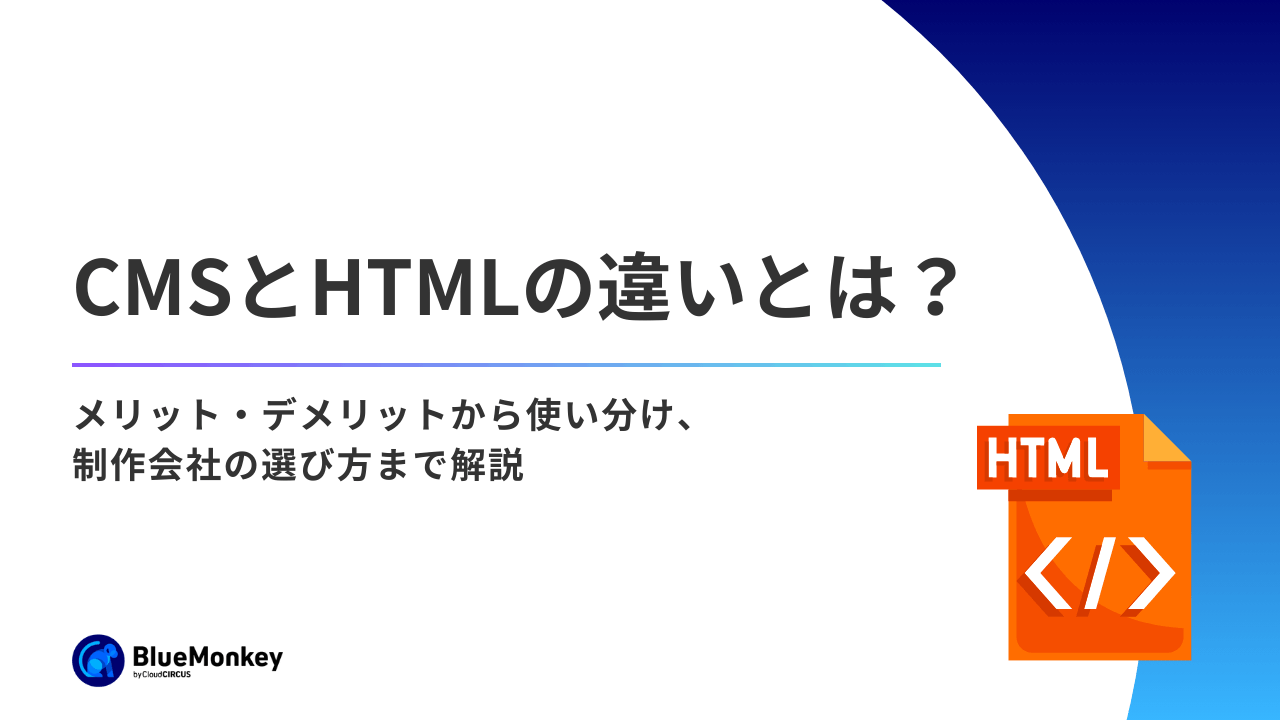【初心者向け】ホームページ制作とは?作り方や基礎知識を解説
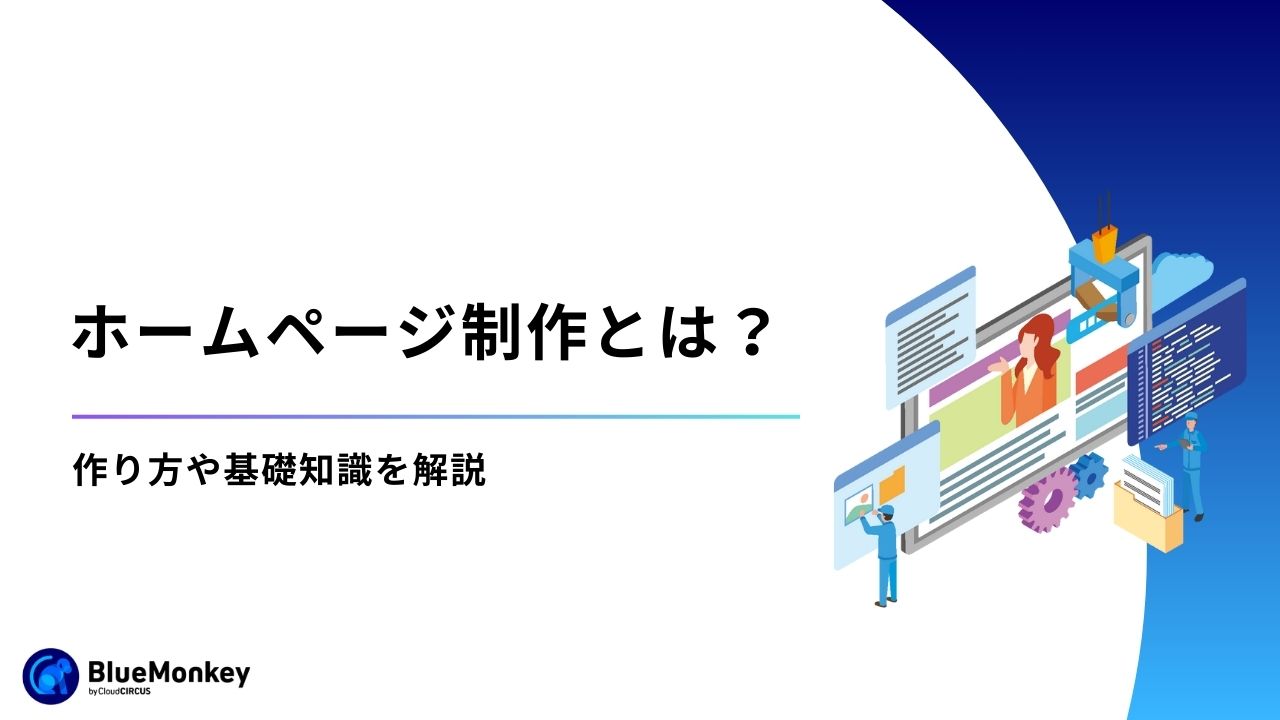
デジタルマーケティングが企業の成長戦略において重要な位置を占める現在、多くの製造業企業でホームページ制作の必要性が高まっています。
しかし、「どこから始めればよいのか」「どのような点に注意すべきか」といった疑問を持っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
本記事ではそんな方に向けて、ホームページ制作の基礎知識から実践的なポイントまで、初心者の方にもわかりやすく解説します。
関連記事:ホームページ制作(Web制作)とは?失敗しない制作の進め方から成功事例を解説!
目次
ホームページ制作とは何か?知っておきたい基本知識を解説
ホームページ制作の定義と目的
ホームページ制作とは、インターネット上に公開されるWebサイトを作成する一連の作業を指します。
具体的には、テキスト、画像、動画などのコンテンツを用意し、Webブラウザで閲覧できるようにデザインし、プログラミングによって構築するプロセスです。その目的は多岐にわたりますが、主に企業や個人の情報発信、商品やサービスの紹介、ブランドイメージの構築、オンラインでの集客や販売促進、顧客とのコミュニケーションなどが挙げられます。
現代において、Webサイトはビジネス活動における重要なプラットフォームとなっています。
Webサイトとホームページの違い
「Webサイト」と「ホームページ」という言葉は、日本ではしばしば混同されて使われますが、厳密には異なる意味を持ちます。
Webサイトとは、複数のWebページがまとまって構成されたウェブ上の情報集合体全体を指す広義の言葉です。
一方、「ホームページ」は、Webサイトの「トップページ」や「玄関ページ」を意味することが本来の定義です。しかし、日本ではWebサイト全体を指して「ホームページ」と呼ぶ慣習が広く定着しています。
本記事では、一般的な理解に合わせて「ホームページ制作」という言葉を使用し、Webサイト全体を構築する意味合いで解説を進めます。
企業におけるホームページの重要性
企業にとってホームページは、現代のビジネスにおいて不可欠な存在です。
第一に、企業の信頼性やブランドイメージを確立する上で重要な役割を果たします。顧客は企業の情報を得るためにまずWebサイトを検索することが多く、その内容やデザインが企業の第一印象を大きく左右します。
第二に、24時間365日、時間や場所を問わず顧客に情報を提供できる強力な情報発信ツールとなります。これにより、製品やサービスの紹介、最新ニュースの告知、採用情報の公開などを効率的に行えます。
第三に、潜在顧客の獲得や売上向上に直結するマーケティングツールとしての機能も持ちます。SEO対策やWeb広告と連携することで、より多くのユーザーにリーチし、問い合わせや購入へと誘導することが可能です。
このように、ホームページは企業の顔として、またビジネス成長を加速させるための重要な資産となります。
ホームページ制作の基本的な流れ
ホームページ制作は、計画から公開、そして運用に至るまで、いくつかの段階を経て進められます。ここでは、初心者の方でも理解しやすいように、その基本的な流れをフェーズごとに解説します。
企画・戦略設計フェーズ
ホームページ制作の最初の段階は、土台となる「企画」と「戦略設計」です。このフェーズでサイトの目的やターゲットを明確にすることで、その後の工程がスムーズに進みます。
ホームページを作る目的は何か、どのような成果を達成したいのかを具体的に設定します。例えば、「企業の認知度向上」「商品やサービスの売上増加」「人材採用の強化」など、具体的なゴールを定めることが重要です。
次に、どのようなユーザーにサイトを訪れてほしいのかを明確にします。年齢、性別、職業、興味関心、サイト訪問の目的などを具体的にイメージした「ペルソナ」を設定することで、ユーザーのニーズに合ったコンテンツやデザインを検討できます。
目的とターゲットが定まったら、サイト全体で伝えたいメッセージや世界観を「サイトコンセプト」として言語化します。これにより、デザインやコンテンツの方向性に一貫性を持たせることができます。
サイトにどのような機能が必要か、どのようなコンテンツを掲載するかなど、具体的な要件を洗い出し、文書としてまとめるのが「要件定義」です。この段階で必要な要素を明確にすることで、後工程での手戻りを防ぎます。
ホームページ制作にかかる費用と期間を明確にし、無理のない予算とスケジュールを立てます。これにより、プロジェクト全体を円滑に進めるための計画が立てられます。
設計・デザインフェーズ
企画・戦略設計フェーズで固めた内容を基に、サイトの構造や見た目を具体的に設計していくのがこのフェーズです。
サイト内のページ構成や階層を整理し、全体像を把握するための「サイトマップ」を作成します。これにより、ユーザーがサイト内で迷わず目的の情報にたどり着けるような導線を設計します。
各ページのレイアウトやコンテンツの配置を視覚的に示す「ワイヤーフレーム」を作成します。これはサイトの骨格となる設計図であり、デザインに入る前に構成の合意形成を図るために重要です。
ユーザーがサイトを快適に利用できるよう、操作性(UI:ユーザーインターフェース)と体験(UX:ユーザーエクスペリエンス)を考慮した設計を行います。使いやすさや分かりやすさを追求することで、サイトの価値を高めます。
ワイヤーフレームとUI/UX設計に基づき、色、フォント、画像などを具体的に配置した完成イメージ図を「デザインカンプ」として作成します。ここでサイトのビジュアルが確定します。
開発・構築フェーズ
設計・デザインフェーズで確定した内容を、実際にWeb上で動作するように形にしていくのが開発・構築フェーズです。
デザインカンプを元に、Webブラウザで表示されるようにHTML、CSS、JavaScriptといった言語を用いてコードを記述します。これが「コーディング」と呼ばれる作業です。
WordPress(ワードプレス)のようなCMS(コンテンツ管理システム)を導入し、コンテンツの追加や更新を簡単に行える環境を構築します。これにより、専門知識がなくてもサイトを運用しやすくなります。
問い合わせフォームやECサイトの決済機能など、動的な処理が必要な場合は、サーバー側で動作するシステムやデータを管理するデータベースを開発・構築します。
サイトに掲載する文章、写真、動画などの素材を用意し、CMSやHTMLファイルに組み込んでいきます。このコンテンツがサイトの価値を大きく左右するため、質にこだわることが重要です。
関連記事:CMSとは?初心者でもわかる意味と基礎知識をわかりやすく解説!
公開・運用フェーズ
サイトが完成したら、インターネット上に公開し、その後も継続的に改善していくことが成功の鍵となります。
公開前に、デザインの崩れ、リンク切れ、機能の動作などを、様々なブラウザやスマートフォンなどのデバイスで徹底的に確認し、不具合がないかを検証します。
ホームページをインターネット上で公開するために、「サーバー」を契約し、サイトの住所となる「ドメイン」を取得して設定します。
最終的な確認が完了したら、いよいよホームページをインターネット上に公開します。この瞬間から、世界中のユーザーが皆様のホームページにアクセスできるようになります。
公開後も、コンテンツの定期的な更新、セキュリティ対策、システムのメンテナンスなどを行い、サイトの健全な状態を保ちます。
検索エンジンにサイトの存在を知らせるための設定(Google Search Consoleへの登録など)や、検索結果で上位表示を目指すためのSEO(検索エンジン最適化)対策の初期設定を行います。これにより、より多くのユーザーにサイトを見つけてもらいやすくなります。
ホームページ制作の方法
ホームページ制作には、大きく分けて「自社制作(インハウス)」「制作会社への外注」「CMS活用」の3つの方法があります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の目的やリソースに合った方法を選ぶことが成功への鍵となります。
自社制作(インハウス)のメリット・デメリット
自社制作、いわゆるインハウスでのホームページ制作は、社内の人材やリソースを活用して行う方法です。
メリット
コストを抑えられる
外部の制作会社に依頼する費用がかからないため、初期費用やランニングコストを削減できる可能性があります。
自由度が高い
社内で制作するため、デザインや機能、コンテンツの内容など、企業の意向を細部まで反映させやすいというメリットがあります。
ノウハウが蓄積される
制作過程を通じて、ホームページに関する知識やスキルが社内に蓄積されます。これにより、公開後の運用や改善もスムーズに行えるようになります。
迅速な修正・更新が可能
社内で完結するため、緊急の修正や情報の更新が必要になった際も、スピーディーに対応できます。
デメリット
専門知識が必要
HTML、CSS、JavaScriptといったプログラミング言語の知識や、Webデザイン、SEO対策、サーバー・ドメインに関する知識など、多岐にわたる専門スキルが求められます。
時間と手間がかかる
企画からデザイン、コーディング、公開、運用まで、すべての工程を自社で行うため、多くの時間と労力が必要です。本業との兼ね合いで、制作が滞る可能性もあります。
品質の確保が難しい場合がある
専門知識や経験が不足している場合、プロの制作会社と比較してデザインの質や機能性、セキュリティ面で劣る可能性があります。
最新トレンドへの対応
Web業界のトレンドは常に変化しており、自社で最新情報をキャッチアップし、対応していくには継続的な学習が必要です。
制作会社への外注時のポイント
専門的な知識やリソースが不足している場合や、高品質なホームページを効率的に制作したい場合は、制作会社への外注が有効な選択肢です。
目的を明確にする
「なぜホームページが必要なのか」「誰に何を伝えたいのか」「どのような成果を期待するのか」など、制作会社に依頼する前に、自社のホームページ制作の目的を具体的に言語化しておくことが重要です。
実績と得意分野を確認する
制作会社の過去の実績やポートフォリオを確認し、自社の業界や目指すデザインテイストに合致しているか、SEO対策に強いかなどを確認しましょう。
見積もりと内訳を比較する
複数の制作会社から見積もりを取り、費用だけでなく、その内訳(企画費、デザイン費、コーディング費、システム開発費など)を詳細に比較検討することが大切です。
コミュニケーションのしやすさ
制作期間中、制作会社との密な連携が不可欠です。担当者との相性やレスポンスの速さなど、円滑なコミュニケーションが取れるかどうかも重要なポイントです。
アフターサポートの有無
ホームページは公開して終わりではありません。公開後の更新、保守、トラブル対応など、どのようなアフターサポートがあるかを確認しておきましょう。
CMS(コンテンツ管理システム)は、Webサイトのコンテンツ(テキスト、画像、動画など)を一元的に管理・更新できるシステムです。専門知識がなくても、ブログ感覚で簡単にホームページを制作・運用できるため、初心者にも人気の高い手法です。
BlueMonkeyを活用したホームページ制作
CMS(コンテンツ管理システム)は、Webサイトのコンテンツ(テキスト、画像、動画など)を一元的に管理・更新できるシステムです。専門知識がなくても、ブログ感覚で簡単にホームページを制作・運用できるため、初心者にも人気の高い手法です。
BlueMonkey(ブルーモンキー)は、日本の中小企業、特にBtoB企業や製造業での利用を想定して開発された国産のクラウド型CMSです。専門知識がなくても直感的に操作できる使いやすさと、強固なセキュリティ、手厚いサポート体制が特徴で、企業のWebサイト運用を多角的に支援します。
初心者の方でも使いやすいCMS
CMSは、多機能になればなるほど、運用者にWebの知識が求められますが、BlueMonkeyは、HTMLの仕組みを知らなくても更新ができるよう、シンプルでわかりやすい機能で構成されています。
テキストの打ち替えや、画像の差し替え、新規ページの作成など、よくある更新作業は、難しいソース画面をいじる必要はなく、ワードやパワーポイントのように「見たまま」編集する感覚で操作できます。
また、インターフェースは、すべて日本語で表示され、直感的に操作することが可能です。
導入事例では、お問い合わせ数の増加やサイト更新コストの削減といった具体的な成果もご覧いただけます。
▼成果事例はこちら
https://bluemonkey.jp/works/results-cases/
▼制作事例はこちら
https://bluemonkey.jp/works/case-web/
充実したサポート体制
はじめてCMSを使用するWeb担当者の方にも安心してご利用いただけるよう、お客様の状況やニーズに合わせた2つのサポート体制をご用意しています。
ひとつは、CMSの操作や技術的な疑問を気軽にお問い合わせいただける「電話・メールサポート」。もうひとつは、お客様が自社でWebマーケティングを実行するための「独自メソッド(DPOメソッド)」です。
どちらのサポートも、BlueMonkeyをご利用のお客様は、無償でお使いいただけます。
また、ユーザーの皆様に、ホームページの運用ノウハウや活用のヒントをお届けするユーザー会も、毎月開催しています。
▼BlueMonkeyの詳細はこちらもご覧ください
ホームページ制作で失敗しないための注意点
よくある制作時のトラブルと対策
ホームページ制作では、計画不足やコミュニケーション不足が原因でトラブルが発生することが少なくありません。
例えば、デザインイメージのずれ、納期遅延、追加費用の発生、さらには著作権や所有権に関する問題などが挙げられます。
これらのトラブルを避けるためには、まず制作会社との間で目的や要件、デザインの方向性を明確に共有することが重要です。
契約書には、作業範囲、納期、費用、修正回数、著作権の帰属などを詳細に明記し、不明な点は事前に確認しましょう。
また、サーバーやドメインは自社で取得・管理することで、将来的なトラブルを回避しやすくなります。定期的な進捗確認や、問題発生時の迅速な対応体制を構築することも大切です。
予算設定と費用対効果の考え方
ホームページ制作の予算は、単に初期制作費用だけでなく、公開後の運用費やメンテナンス費、さらにマーケティング費用も含めて総合的に考える必要があります。
予算設定にあたっては、まずホームページで何を達成したいのか(集客、ブランディング、売上向上など)という目的を明確にし、それに対する費用対効果(ROI)を考慮することが重要です。
例えば、新規顧客獲得を目的とする場合、顧客単価やライフタイムバリュー(LTV)から逆算して、ホームページにかけられる予算を算出する方法があります。
制作費用が安くても、目的を達成できなければ費用対効果は低いと言えます。
複数の制作会社から見積もりを取り、内訳を比較検討することで、適正な費用で質の高いホームページを実現できる可能性が高まります。
セキュリティ対策の重要性
ホームページは公開後、サイバー攻撃の脅威に常に晒されています。特に中小企業はセキュリティ対策が弱いと狙われやすいため、適切な対策が必須です。
不十分なセキュリティ対策は、ホームページの改ざん、個人情報の漏洩、サーバーダウンなどの深刻な被害を引き起こし、企業の信頼失墜につながります。
対策としては、SSL/TLS証明書の導入による通信の暗号化、CMSの定期的なアップデート、強力なパスワード設定と管理、不要なファイルやサービスの削除が基本です。
さらに、ファイアウォールやWAF(Web Application Firewall)の導入は、不正アクセスやWebアプリケーションへの攻撃を防ぐ上で非常に効果的です。
複数のセキュリティ対策を組み合わせ、多層的に防御することで、より安全なホームページ運用が可能になります。
継続的な運用・改善の必要性
ホームページは一度作って公開したら終わりではなく、「生き物」のように継続的な運用と改善が必要です。 運用を怠ると、情報が古くなりユーザーの信頼を失ったり、検索エンジンの評価が低下して集客力が落ちたりする可能性があります。
競合他社も常に情報を更新し、ブラッシュアップしているため、自社も継続的にコンテンツを更新し、情報の鮮度を保つことが重要です。
また、サーバーやドメインの管理、CMSのバージョンアップ、最新のブラウザやデバイスへの対応など、技術的な保守作業も欠かせません。
これらを怠ると、セキュリティリスクの増大や表示の不具合につながり、結果的にホームページの価値を大きく損ねてしまうことになります。
効果的なホームページであり続けるためには、公開後の継続的な運用と改善計画を制作段階から考慮しておくことが不可欠です。
まとめ|効果的なホームページ制作への第一歩
この記事では、ホームページ制作の定義から、具体的な制作の流れ、必要な技術、選択肢、そして公開後の運用・改善まで、初心者の方が知っておくべき基礎知識を幅広く解説しました。
ホームページは、現代において企業や個人の信頼性を高め、目標達成に不可欠なツールです。一見複雑に思えるかもしれませんが、適切な知識と計画、そして継続的な改善を行うことで、初心者の方でも必ず効果的なホームページを制作できます。

この記事を書いた人
クラウドサーカス株式会社 ウェブプロモーション事業部 部長
長谷川 潤
プロフィール
1979年生まれ 福島県出身。アパレル業界でキャリアをスタートし、ECサイトの立ち上げと運用を通じてWebマーケティングの世界へ。その後、デジタルマーケティング領域の専門性を深めるべく、スターティアラボ株式会社(現:クラウドサーカス株式会社)に入社。2009年以降、10年以上にわたりBtoB企業向けのWebサイト構築を手がけ、コンバージョン最大化を軸に多数のプロジェクトを支援。2023年からはウェブプロモーション事業部の責任者として、新規顧客獲得を目指すBtoB企業のマーケティング活動を牽引しています。